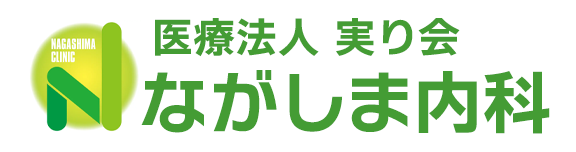生活習慣病

これらの疾患に共通するリスク因子には、動脈硬化、高血圧、高脂血症、糖尿病があります。
代表的な疾患
高血圧
高血圧は、収縮期血圧(上の血圧)が140mmHg以上、または拡張期血圧(下の血圧)が90mmHg以上の状態を指し、家庭での測定値であれば135/85mmHg以上を指標とします。
高血圧自体に明確な症状は現れないことがほとんどですが、放置すると脳卒中、心臓病、腎臓病などのリスクが高まり、重大な健康問題を引き起こす可能性があります。
ほとんどの高血圧は本態性高血圧と呼ばれ、特定の原因によるものではなく、生活習慣が大きく関与しています。そのため、食生活の改善が非常に重要で、特に食塩の摂取量を日に6g未満に抑えることが推奨されています。
また、二次性高血圧と呼ばれる特定の医学的原因に基づく高血圧の場合は、その原因の特定と治療が必要です。
これには適切な診断と個別の治療計画が必要とされ、当院ではそれに応じた対応を行っています。
脂質異常症
血液中のLDLコレステロール(「悪玉」とも呼ばれる)が140mg/dL以上、中性脂肪が150mg/dL以上である、またはHDLコレステロール(「善玉」とも呼ばれる)が40mg/dL未満である状態を指しています。
特に、LDLコレステロールが120~139mg/dLの場合は境界域とされます。生活習慣の欧米化により、日本人のLDLコレステロールや中性脂肪の数値が上昇し、脳梗塞や狭心症、心筋梗塞など動脈硬化に関連する病気の発生率が増加しています。
これらのリスクを抑えるためには、食事内容を見直し、禁煙、適度な運動が重要です。
心血管疾患
喫煙、高血圧、LDLコレステロールの上昇は、冠動脈(心臓の血管)の動脈硬化を促進し、狭心症や心筋梗塞のリスクを高めます。狭心症は、冠動脈の血流が悪くなり、特に運動時に胸痛を感じる状態を指します。
これは心臓への酸素供給が不足している状況を示しています。
一方で、心筋梗塞は、冠動脈が血栓で完全に詰まり、心筋細胞が壊死(死滅)する重篤な状態を指します。
メタボリックシンドローム
メタボリックシンドロームは、複数の心血管疾患のリスクファクターが重なる状態で、主に内臓脂肪の蓄積による肥満が特徴です。具体的には、腹囲が男性で85cm以上、女性で90cm以上の内臓肥満が基準の一つとされています。
さらに、以下の3つのリスク因子—高血圧(130/85mmHg以上)、脂質異常症(HDLコレステロールが40mg/dL以下または中性脂肪が150mg/dL以上)、高血糖(空腹時血糖が110mg/dL以上)—のうち、2つ以上が認められる場合にメタボリックシンドロームと診断されます。