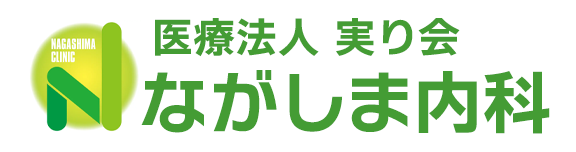栄養指導

食事を見直す必要があると診断されたご本人だけでなく、そのご家族の方など、どなたでもご参加いただけます。
こんな指導をします
- 減塩のコツ
- 食事のバランス
- スライドを使った説明
糖尿病教室の取り組み
当院が力を入れて取り組んでいることの一つが糖尿病教室です。
糖尿病教室では医師、看護師、薬剤師、管理栄養士が糖尿病についてや治療についてお伝えしています。
当院の糖尿病教室の一番の目的は、通院でも血糖値を改善し、維持できるようにすることです。
入院して食事や生活を改善するという方法もあり、この場合も糖尿病について学ぶ時間を設けているところが多いです。
しかし、退院すると病院と同じような生活をすることは難しく、結局もとの生活に戻ってしまう場合もあると思います。
そこで当院では通院しながら、ご自分の生活に合わせてできることから取り組んでいただきたいと考えています。
そのヒントを得る場として、糖尿病教室を開催しています。
糖尿病の基本的な内容が中心ですが、少しでも知識を持っていることで意識が変わり、良い治療につながります。
また、糖尿病歴が長い方でも、今の生活を見直すきっかけにもなりますし、新しいことを得る機会にもなると思います。
糖尿病と診断された方だけでなく、そのご家族の方、将来糖尿病が気になる方など、どなたでもご参加いただけます。
スライドを使ってお話しするだけでなく、クイズや患者様同士の交流の時間を作るなどして、楽しく学んでいただけるように取り組んでいますので、多くの方にご参加いただけたら嬉しいです。
レシピの紹介
試食などを行うこともあり、おいしく食べられるとご好評です。
- スパニッシュオムレツ

- ごぼうと人参のさっぱり和え

- じゅわっとなすの生姜和え

フットケアについて
血糖値が高い状態が続くと、血液の流れが悪くなったり、細菌などに対する抵抗力が落ちます。
そのため、少しの傷でもしっかりと手入れしなければいけません。
特に足は見る機会が少ないため注意が必要です。
今回はフットケアのポイントをお話しし、実際にどのような状態になるのか写真を見ていただきました。夏に比べてはだしになる機会は少ないと思いますが、毎日足をチェックすることが大切だということを学んでいただきました。
みんなでエクササイズ
新型コロナウイルスがなかなか終息せず、思うように出かけられない日々が続いています。
その結果、活動量が減り、反対に間食が増えてしまうというお声をよく耳にします。
そこで今回は、自宅でできる運動をご紹介し、実際に皆さんでやってみました。
参加した方からは「身体がポカポカした」「いつものストレッチに取り入れてみます」といった感想をいただきました。
年末年始の過ごし方
年末年始は1年の中でも体重が増加しやすく、その後のHbA1cを悪化させやすい時期です。そこで、年末年始も血糖値を良好に保つために気をつけていただきたいことを説明しました。
野菜から食べること、よく噛んで食べることは普段から気を付けていただいていることですが、この他にもだらだらと食事を摂らないことや目につくところに食べ物を置かないことを説明しました。
また間食が増えないようにルールを決めること、毎日体重を測定することもポイントに挙げました。
これまでの年末年始の過ごし方を振り返り、今後の食事療法に対するモチベーションアップに繋げられました。
院長に聞く!糖尿病のギモン
今回は患者様から糖尿病について聞きたいこと・知りたいことを院長が回答するという質問形式で行いました。
患者様からはウォーキングを毎日する場合としない場合ではHbA1cに差があるか、インスリンの出る量によってHbA1cは変わるのか、ビタミン剤やコラーゲンなどの健康食品は飲んでも良いか、などの質問が挙がりました。
これらの質問に対して院長は、有酸素運動と合わせて筋力トレーニングを行うことが効果的であることを話したり、日本人と糖尿病の関係や気を付けたい食品などを説明しました。
患者様からは「分かりやすくて勉強になった」、「今日からまた頑張ります」といったお声をいただきました。
糖尿病の三大合併症について
糖尿病は血糖値を正常にコントロールすることが重要です。
糖尿病は、予備軍から動脈硬化が発症・進展します。
糖尿病と診断されても自覚症状がないからと治療を怠れば、神経障害、網膜症、腎症を発症します。
糖尿病の治療では、できるだけ初期の段階で血糖コントロールを開始することが大血管障害や細小血管障害といった糖尿病合併症のリスクを回避する上で重要です。
これだけは押さえておきたい!~糖尿病と薬~
糖尿病の薬は作用方法や作用時間などによっていくつか種類があります。
自分が飲んでいる薬はどのような薬なのか知っておくことで正しい治療につながります。
そこで今回は薬剤師さんから糖尿病の薬について説明していただき、その特徴を学んでいただきました。
例えば飲んでからすぐに効き始める薬は飲んでから食事までの時間が空くと低血糖を起こすリスクが高まるため食直前に飲むことや、糖を尿と一緒に出す薬は脱水に注意するといったお話がありました。
どんな薬が処方されているか、薬に関心を持っていただけたらと思います。
検査について
今回は糖尿病の検査についてお話ししました。
検査にもいくつか種類があります。
糖尿病の状態を調べる検査、合併症を調べる検査、そして体重や血圧も大事な検査になります。
それぞれの検査で何を調べているのか、何のために調べるのか知っていただくことで、自分の状態を知り、前向きな治療につなげられたらと思っています。
レッツ・ダイエット!
始めに運動と血糖値の関係について学んでいただきました。
その後、雨の多いこの時期に家の中でも運動していただけるよう、いくつか運動を紹介し、実際にやっていただきました。
運動しているときの呼吸や使っている部位を意識しながら、できる範囲で取り組んでいただきました。
少しつらい運動もありましたが、みんなでやることで楽しく行うことができました。
減塩教室の取り組み
当院では糖尿病教室同様、減塩教室にも力を入れております。
高血圧の原因は遺伝的な要因に加えて塩分の摂り過ぎ、肥満、喫煙、運動不足などが挙げられます。
血圧が高いと動脈硬化が起こり、心筋梗塞、脳梗塞の原因となりますので血圧を安定させることが大切です。
そこで減塩教室では医師、看護師、管理栄養士から、高血圧についての理解を深め食事や自らの生活習慣を改善することができるよう、様々なテーマについてお話しします。
高血圧や心臓病と診断されただけでなく、そのご家族の方などどなたでもご参加いただけます。
スライドを使ってお話しするだけでなく、クイズや患者様同士の交流の時間を作るなどして、楽しく学んでいただけるように取り組んでいます。
レシピの紹介
- カレーソースの鶏肉ソテー

血圧の正しい測り方
血圧は体の状態を知る上で、大切な指標です。血圧は24時間変動しており、常に一定というわけではありません。
正しい測り方でないと正確な数値が出ません。自身の血圧を正確に知るためには、毎日の家庭での血圧測定が大切です。
今回は実際に血圧計を用いて、測る時の姿勢やポイント、血圧計の種類別の測り方を説明し正しい測定方法を知っていただきました。
減塩の工夫 管理栄養士
日本人の塩分摂取量は、1日あたりの平均男性11.0g、女性9.3g(平成30年度国民健康・栄養調査より)ですが、厚生労働省が生活習慣病の予防を目的に示した目標量は、1日平均男性7.5g未満、女性6.5g未満となっています。(日本人の食事摂取基準2020より)
過剰な塩分摂取は、体内の血液量、心拍出量の増加により血圧が上昇します。
そこで今回はただ薄味にするのではなく、楽しく美味しく続けられる減塩食の工夫についてお話しました。
一度、ご自身の食生活を振り返り、小さな工夫から始めていただきたいです。
知っておきたい減塩のコツ 管理栄養士
塩分の摂りすぎは高血圧に繋がります。現在、日本人の平均塩分摂取量は目標量より多いのが現状です。
「高血圧と言われたら減塩」と分かっていても自分で料理をしない方、外食が多い方など食生活は人様々です。今回は料理をする時、外食をする時における食べ方の工夫など、普段の食生活に合わせて簡単にできる減塩方法についてお話ししました。